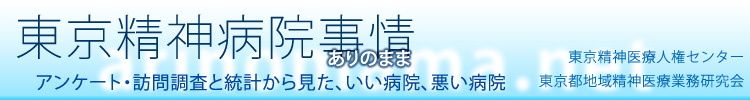■ 調査概要 |
| ■2004年精神病院訪問調査 |
- 第1版から3版までは、精神病院統計に基づいて出版してきたが、前回第4版2000年版で、初めて病院訪問を実施し、精神病院統計と併せた報告をした。
- 病院訪問については、①訪問調査を依頼したときの反応で、その病院の姿勢がある程度わかる。②私たちの訪問により、病院側はそれなりの緊張を強いられるとともに、現在院内で行われていることを振り返るきっかけになるのではないか。 ③入院している人たちにとっては外との繋がりを感じられるのではないか。 ④精神病院をめぐる状況は大きく変化しているが、精神病院の実態に触れ、変化を肌で感じられるのではないか。等の意義が確認された。
- 2004年第5版の準備を始めるに当たっても、前回同様、事前に各病院に2004年都内精神病院アンケート(第一部 病院全体用・第二部 見学病棟用) questionnaire.pdfに答えていただいた上で、それをふまえて訪問調査を実施することとした。
- 前回は、全体が総花的に流れたという反省に立ち、今回はねらいを、社会的入院の退院促進と急性期医療のあり方、精神病院内の人権問題にしぼった。
- ひとつめは、社会的入院者72,000人を10年間で退院促進すると厚生労働省が方針化して久しく、各地で退院促進事業も取り組まれているが、実際に各精神病院では、長期入院、社会的入院をどのように考え、退院のためにどんな活動をしているか。
- 急性期医療については、東京精神医療人権センターへの相談の中に、夜間救急入院時を中心として、急性期治療時に身体拘束されたこと、電気けいれん療法に誘導されたこと等への苦痛・不満の訴えが増えていることから、各病院での急性期治療の実態を明らかにするため。
- 3点目は、やはり人権センターの相談活動の中で、通信面会の自由にはじまる入院時の基本的人権が精神保健法への改正後努力してきた後、再び後退してきているのではないかと感じることから、点検の意味で。
- また、前回は訪問した調査員によって、結果レポートの差が大きかったという反省があり、今回は事前に勉強会を開いて調査員は必ず参加することとし、レポートも複数の目で見直すこととした。
|
| ■病院訪問までの準備と経過 |
2004年3月 調査の軸となる班長会を組織する。
2004年4月 「精神病院での人権その1」をテーマに勉強会
講師-東京精神医療人権センター小林信子氏
2004年5月 「精神病院での人権その2」をテーマに勉強会
講師-大阪精神医療人権センター山本深雪氏
2004年6月 精神病院調査説明会と調査員募集
2004年6月 「長期在院・社会的入院問題とは何か」をテーマに勉強会
講師-精神病院PSW
2004年7月 宿泊勉強会
1 「いわゆる急性期治療と電気けいれん療法」をテーマに勉強会
講師-診療所医師
2 精神病院統計の読み方
3 病院訪問調査を想定したロールプレイ
4 アンケート用紙の作成
2004年8月 病院長宛に調査の依頼とアンケート用紙を送付
2004年8月 「第三者評価制度への挑戦」をテーマに勉強会
講師-精神病院事務長
2004年8月 二日間にわたり全調査員対象に病院訪問調査を想定したロールプレイ
2004年9月~2005年4月
病院訪問調査実施する。調査員4人をチームとして訪問。
調査に参加したのは実数36名、延べ129名であった。
2005年4月~8月
訪問調査のまとめをする。
| 調査を依頼した病院 |
80ヶ所
|
| 訪問調査した病院 |
33ヶ所
|
| アンケートのみ返送してきた病院 |
8ヶ所
|
| 調査を受け入れなかった病院 |
39ヶ所
|
|
| ■データの見方 |
- 訪問調査を受け入れた33病院の病院レポートが中心であるが、アンケート回答のみの病院、調査を受け入れなかった病院もそれぞれに応じて掲載した。
- 訪問調査した病院については、見学した病棟での見聞と応対してくれた方の話を中心に訪問レポートをまとめ、それについての私達のコメントを付けた。病院からのアピールも掲載。アンケート回答のあった病院については、長期入院への考え方と退院促進の項目の回答を抜粋して掲載した。
- 点数やレポート、コメントに引用した数字は2003年6月30日現在の東京精神病院統計に基づいている。
- 老人性痴呆症は、この調査中に認知症と名称変更されたが、この本では当初の名称で統一した。
|
| ■レーダーチャートの見方と基準 |
- 8項目について5段階に分け、40点満点とした。つまり数字が多いほうが相対的に活動性が高い、あるいは望ましいものとして表した。レーダーチャートの面積が多い方がよいということになる。
- 8項目中以下の3項目を、これまでの4版と指標を変更した。
- 「3ヶ月未満在院者率」→「1年未満在院者率」 「4年以上在院者率」→「3年以上在院者率」 「死亡退院率」→「家庭・社会復帰施設への退院率」
- この間、全体的に点数が上がってきて、過去4版で用いてきた基準では4~5点に集中し、病院間の差が見えにくくなってきた。東京都全体でも1989年に24点であったものが、2003年統計では29点に上昇した。そこで、東京都全体の平均が各指標3点、合計24点になるよう刻み方を修正した。
-
- ベッド回転率
年間にどのくらいの入退院があるかを示す。
回転率100%ということは、1年間にその病院の病床数と同じ数の入退院があったということになる。したがって回転率が低いほど長期入院が多く不活発な病院ということだが、逆に回転率が高くても機械的な転院によって数字上の回転のみが上がっている病院もあり吟味が必要である。
|
ベッド回転率=
(入院者数+退院者数)/2/今期末患者数×100 |
1:50%以下
2:50%超100%以下
3:100%超150%以下
4:150%超300%以下
5:300%超 |
|
- 1年未満在院者率
これまで全入院者のうち在院期間が1年未満の割合。これまで3ヶ月未満で見てきたが、経験則として入院後1年を超えると退院が難しくなること、そのため1年後残留率や1年以上入院者の退院率などが広く分析の対象となってきていることから、今後1年未満在院者率を指標とすることにした。
|
1年未満在院者率=
在院1年未満患者数/今期末患者数×100 |
1:20%未満
2:20%以上30%未満
3:30%以上40%未満
4:40%以上50%未満
5:50%以上 |
|
- 3年以上在院者率
超長期在院者の全体に占める割合。
歴史の長い病院はどうしても高くなるきらいがあるが、他の指標とあわせて見ると「入れっぱなし」型の病院かどうかわかる。これまで4年以上でとってきたが、都内全体の点数が上がってきたこと、今回の私達のアンケート調査でも30病院(73%)が「1年以上を長期入院とみなす」と回答していることから、今後3年以上在院者率で見ていく(5段階の基準は変更なし)ことにした。
|
3年以上在院者率=
在院3年以上患者数/今期末患者数×100 |
1:65%以上
2:55%以上65%未満
3:45%以上55%未満
4:30%以上45%未満
5:30%未満 |
|
- 家庭・社会復帰施設への退院率
これまで死亡退院率をみてきたが、以前は老人病院を除き、死亡退院率の高い病院が入退院の動きが少なく悪い病院、低い病院が良い病院という傾向があったが、身体合併症の治療のための転院も行うようになり、死亡退院率の高低のみでは良い・悪いの指標とならなくなったと考えた(もちろん老人病院でもないのに死亡退院率が高率な滝山病院(64%)や東京新生病院(50%)などは、引き続き大問題病院であるが)。そこで今回から退院のうち死亡退院と転院を除く、自分の家・社会復帰施設、即ち生活の場への退院率を新しい指標とすることにした。
|
家庭・社会復帰施設への退院率=
家庭・社会復帰施設への退院数/年間退院者数×100 |
1:49%未満
2:49%以上69%未満
3:69%以上84%未満
4:84%以上94%未満
5:945以上 |
|
- 常勤医1人当りベッド数
職員の充足状況の指標の一つ。
非常勤医に依存している病院は一人あたりのベッド数が多くなる。今回基準を少しアップした。
|
常勤医1人当りベッド数=
ベッド数/常勤医師数 |
1:81床以上
2:61床以上81床未満
3:41床以上61床未満
4:21床以上41床未満
5:1床以上21床未満 |
|
- 看護者1人当りベッド数
看護者は病院のマンパワーの大きな部分を占める。人手が多いからよい病院とはストレートに言えない面もあるが、人手が少なくてもよい病院というのはまれなことである。やはり、今回基準を少しアップした。
|
看護者1人当りベッド数=
ベッド数/常勤看護者数 |
1:4床以上
2:3床以上4床未満
3:2床以上3床未満
4:1床以上2床未満
5:1床未満 |
|
- コメディカル職員1人当りベッド数
多様な職種によるチーム医療は重要である。
PSW、臨床心理、作業療法士(OT)などのコメディカル職員がどれだけ配置されているかを見る。医師、看護者と同じく基準を少しアップした。。
|
コメディカル職員1人当りベッド数=
ベッド数/(常勤のPSW数+心理数+OT数) |
1:51床以上(職員0の場合も含む)
2:36床以上51床未満
3:26床以上36床未満
4:16床以上26床未満
5:1床以上16床未満
|
|
- 1ヶ月1床当り外来数
外来活動が活発かどうかを示す。
交通の便や総合病院であるか等に左右される。大規模にデイケアを行っている病院で増える傾向にある。交通の便のよいところにサテライトクリニックを開く病院も増えているので、ここに表れない外来活動もあるが、全体として15年前よりかなりアップしてきているので、やはり基準の変更を行った。
|
1ヶ月1床当り外来数=
年間外来延べ数/ベッド数/12 |
1:1人未満
2:1人以上3人未満
3:3人以上6人未満
4:6人以上12人未満
5:12人以上 |
|
|